アロマケアの種類
精油は作用は嗅覚からの吸入とオイル使用などによる皮膚からの吸収で、体内へさまざまな有用作用をもたらします。
嗅覚からの吸入では、脳への刺激により体をリラックスさせたりしますし、皮膚塗布によるオイルケアでは血流や体液に届いた精油成分によって各臓器にさまざまな作用が現れます。
実際に私たちがそれらの精油の作用をどのようにして受けられるのか?ということについて、ご紹介します。
正しい使用方法を今一度確認していただき、体調不良の改善等に役立てていただけたら幸いです。
基本情報
使ってはいけないケース(禁忌情報)
作用に関する注意事項
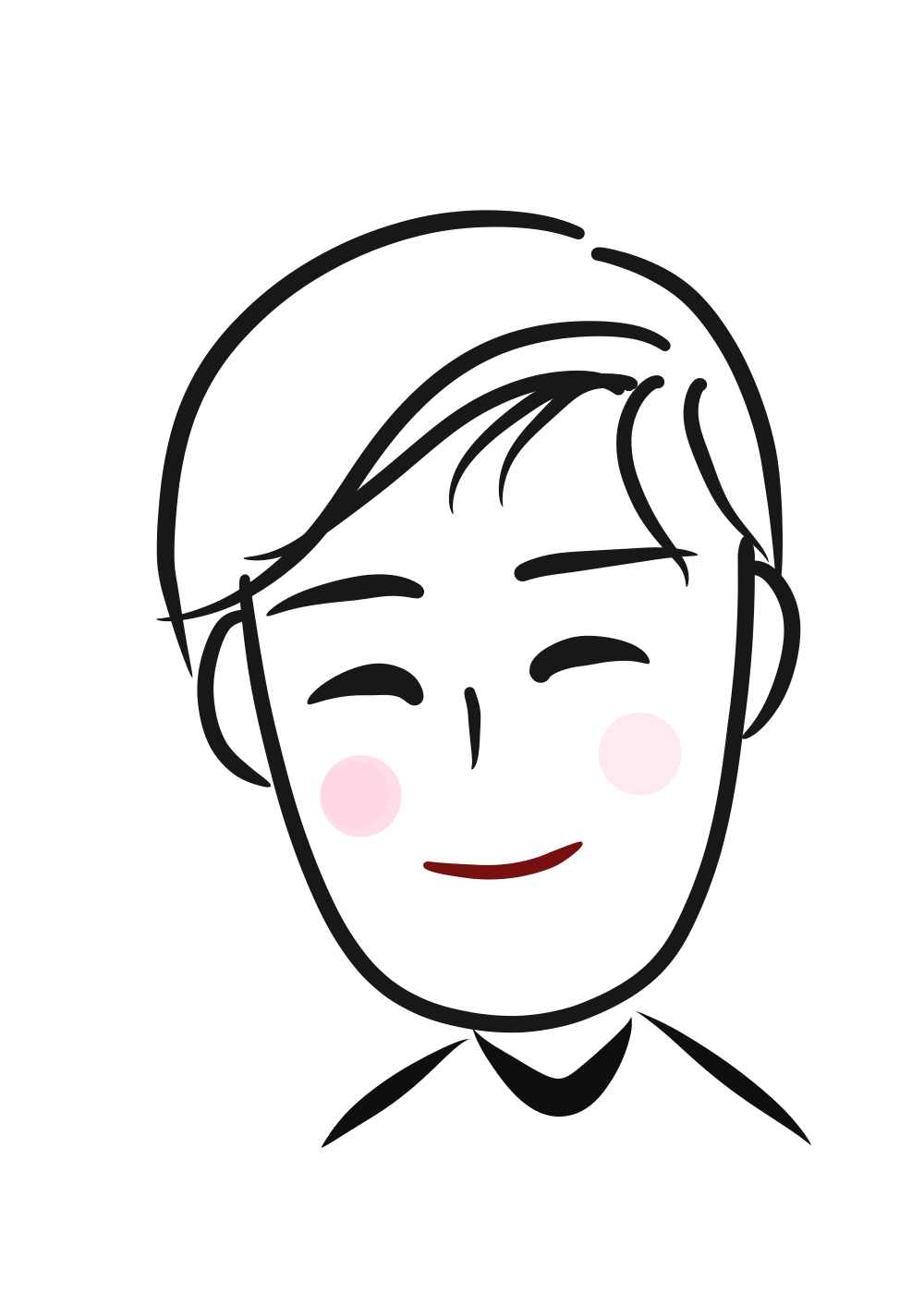
一般販売ですぐ精油は買えるけど、
誰でも使っていいの?

成分が体に入るものなので、
誰でもOKという訳にはいかないんです。
しっかり基本事項を覚えておいてください。
まずは、ご使用にあたり年齢別の「基本情報」をお伝えします。
これは、どんな人にどんな使い方が可能なのかという情報です。
ここでは、JAA日本アロマコーディネーター協会推奨を基準として説明します。
赤ちゃん、幼児、子供、に対しては精油を極力薄めて使用することを推奨しています。
- 0~1歳
ラベンダー/カモミールローマン
<室内芳香のみ 使用方法制限あり>
- 1~7歳
ラベンダ―/カモミールローマン/ティーツリー
<使用方法と濃度に制限あり>
- 8~14歳
上記以外も使用可能
<濃度に制限があり>
- 65歳以上
同じく上記以外も使用可能
<濃度に制限あり>
次に、「使ってはいけないケース」(禁忌情報と呼びます)についてお伝えします。
これは、疾患をお持ちの方や、投薬中の方々については体内へ精油の成分を入れるのは安全性に問題があるという意味です。
✖ 1歳未満、高齢者には使用しない
✖ 飲まない
✖ 精油の原液を直接肌につけない(一部塗布できるものがあります)
✖ 敏感肌の人やアレルギー疾患をお持ちの方はパッチテストを推奨
✖ 通院中、服薬中の方は医師に相談
そして最後に、精油の「作用に関する注意事項」をご紹介します。
精油には様々な種類があり、抽出方法もたくさんあります。
成分分類ごとに作用も分かれており(有用作用が判明しており)、一つの精油でもいくつかの成分で構成されているため、数種類の有用作用を持ちます。
たとえば、「ローズマリー」。ただローズマリーといってもいくつかあります。
ローズマリーシネオールを例にとってみましょう。
ブレンドしたときの香りは中間、早くから香ってなくなるでもなく、ずっと最後まで残っているでもないという感じの香り方です。
抗感染症、抗菌では、黄色ブドウ球菌や大腸菌、クレブシエラ属(肺炎に関係する菌)、プロテウス属(腸内細菌)などに作用します。
呼吸器全般に有用作用をもち、消火器では肝臓を強くしたり、胆汁を分泌します。
循環器では静脈動脈の循環障害に関与し、筋肉や神経にも働きかけます。
婦人科、心や精神に対する作用、もちろん肌にも有用作用をもっています。
このように、ひとつの精油でも様々な有用作用が確認されており、目的に合わせて他の精油とブレンドされたりして使用されます。
そして忘れてはないらないのは、ほとんどの精油に注意事項が存在するということです。
ローズマリーシネオールで言えば、婦人科の作用に優れていることもあり、妊娠中であったり月経に不順や障害がある方、高血圧やてんかんをお持ちの方にはご使用いただけません。
このように、精油別の注意事項はとくに、精油が体内に入ってしまう成分であるため、セラピストが厳重に注意している点です。
トリートメントでは、全身に精油がいきわたることで、トリートメント前との感覚が大きく変化したことを感じる方もいらっしゃいます。
ご自宅で楽しまれる場合も、上記の注意事項が存在することをよくご理解されてご使用ください。
精油の使用方法
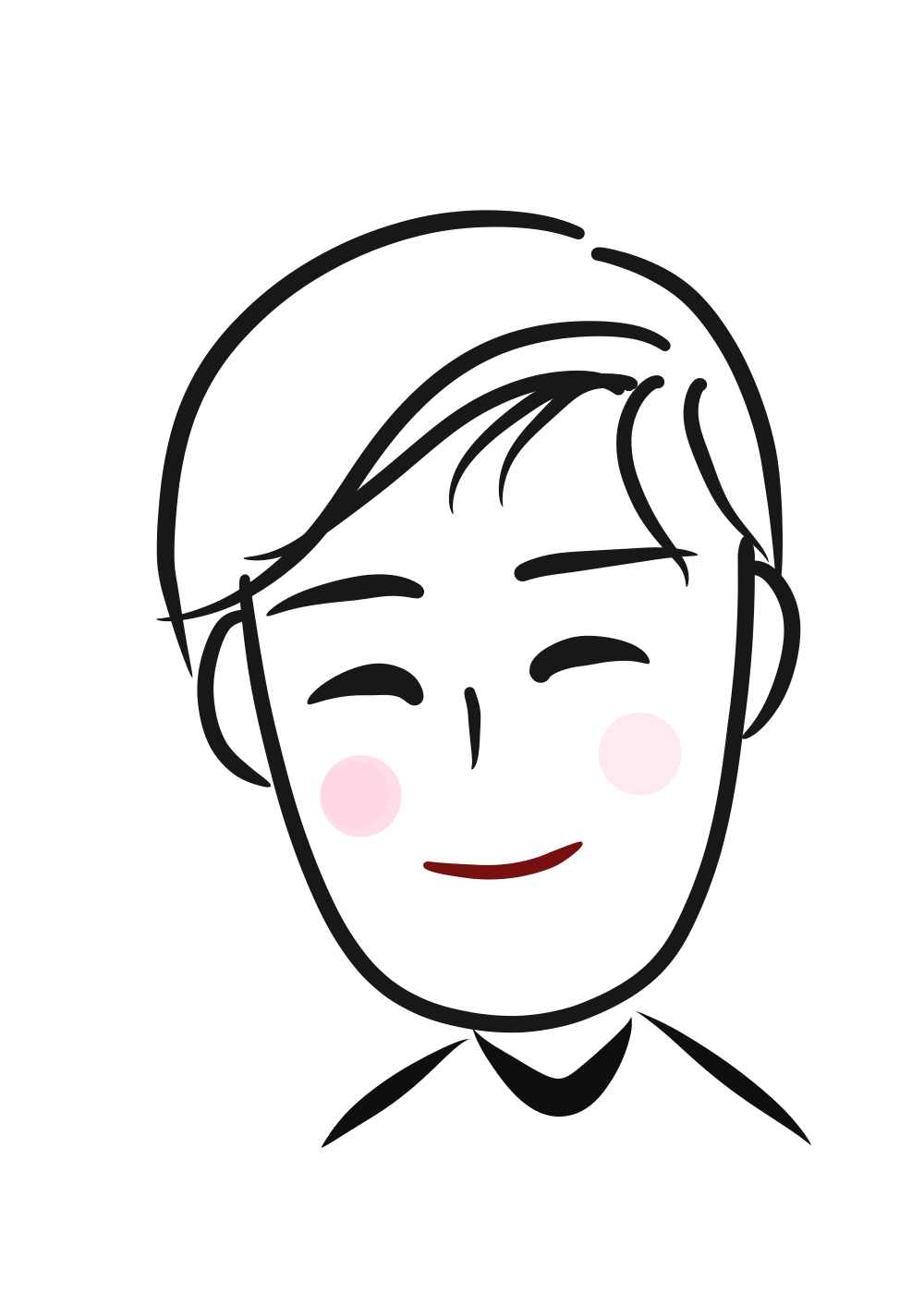
では、精油の正しい使い方って
どんな感じなの?
香りを嗅ぐ他にもあるの?

芳香だけで考えても、いくつか方法があります。
ご自身に合った使い方を見つけてみてください。
ここでは、主に一般的な使用方法をご紹介します。
ご自身でのご自宅のケアなどの参考にしていただけたらと思います。
- バスタイムでの呼吸吸収/皮膚吸収
入浴時に精油を含んだバスソルトやバスミルクを浴槽に入れ、精油の成分を皮膚から吸収します。
- 手浴、足浴(皮膚吸収)
入浴よりももっと手軽に、身体への作用を楽しむことができます。
洗面器などにお湯をはり、精油をたらして手や足を入れ温めます。
ポイントは首まで入れること、手首、足首のことです。
- ハンカチやティッシュを使った呼吸吸収
呼吸器の不調や、急な体調不良、外出時や勤務中など、ほんの少しの対応でその時の身体の状態をよい方向へ向かわせることができます。
ハンカチやティッシュなどに精油を含んだ化粧水やスプレーをつけ、吸入するだけです。
ただ、ハンカチを用いる場合は汚れてもいいものにしましょう。
- マグカップでの呼吸吸収
マグカップにお湯を注ぎ、精油を加えて吸入する形です。
仕事中のデスクの上などでも、気軽に吸入できます。
これは間違っても飲んではいけません。
ご家族が勘違いして飲んでしまわないように注意も必要です。
- ボウルでの呼吸吸収
大きめのボウルへお湯を入れ精油を加えて、吸入する方法です。
タオルなどを頭に被ることでボウル上部の空気中の精油成分の密度を上げ、効果的に吸入することができます。
精油が口から体内に入ることを防ぐため、調理用のボウルとは別のアロマ専用ボウルを用意してください。
- アロマ専用デフューザーを使った呼吸吸収
今はアロマ専用デフューザーの種類も豊富ですね。
加湿に加えて殺菌消毒作用のある精油を使用すれば、お部屋の空気を浄化しながら香りを楽しむこともできます。
ただし、一般のデフューザー(アロマ用でないもの)には精油を入れてはいけません。
- タオル湿布での皮膚吸収
お湯と精油を入れた洗面器にタオルを浸し絞って患部へ当てることで、湿布として用いることも可能です。
上の場合は温湿布ですが、冷水を使えば冷湿布になります。
- オリジナル化粧品としての皮膚吸収
精油とクラフト材(オイルやエタノール、ソープ、みつろう、シアバターなど)を用いて自分に合った精油のお化粧品を作ることができます。
- セラピストによる施術(オイルトリートメントでの皮膚吸収)
トリートメント用のオイルに精油を含ませて、全身や体の各部位に対して皮膚に塗布していくものです。
顔、体、手、足、原則的には髪の毛にもオイルは塗布できますので、体の全てに精油は使用できます。
目的は、精油を体に届けるのみのオイルケア、マッサージ効果も含んだオイルケア等店舗により色々あります。
ダイエットを目指しているなら、体内脂肪を燃焼させる精油を使いそれに合わせた施術を行います。
リラックスが目的であれば、リラックス作用のある精油での施術になります。
施術の手技については、日本国内ではさまざまなパターンがあります。
サロン独自のという店舗が多いかもしれません。
おわりに
このように、アロマケアとして体内へアプローチできる方法は多岐に渡ります。
他にも使用方法はたくさんありますが、日常でお掃除などに使用できる方法などは、また別途記述したいと思います。
少しでも興味をもってくださって、トライしていただけるキッカケになったら嬉しいです。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。
アロマは永遠にあなたの側にあります。
すぐ手の届くところに。